2011年02月18日
浦添城(グスク)について
国指定史跡 浦添城跡
浦添グスクは、首里城以前の中山(ちゅうざん)王城として知られています。
発掘調査から、14 世紀頃の浦添グスクは、高麗系瓦ぶきの正殿を中心に、堀や石積み城壁で囲まれた巨大なグスクで、周辺には王陵・寺院・大きな池・有力者の屋敷・集落などがあったと考えられています。
のちの王都首里の原形がここでできあがっていたようです。
 王都が首里に移された後、浦添グスクは荒廃しますが、1524 年頃から1609 年の薩摩藩の侵攻までは浦添家の居館となりました。
王都が首里に移された後、浦添グスクは荒廃しますが、1524 年頃から1609 年の薩摩藩の侵攻までは浦添家の居館となりました。
去る沖縄戦では、日米両軍の激しい戦闘により、戦前まで残っていた城壁も大部分が破壊されました。
これまでの発掘調査では、石積み城壁の基礎や、敷石遺構、建物跡などが良好に残っていることが確認されています。
1989年、国指定史跡となり、史跡浦添城跡復元整備事業を進めているところです。
数十年後には世界遺産に追加登録されることが期待されます。
浦添グスクは、首里城以前の中山(ちゅうざん)王城として知られています。
発掘調査から、14 世紀頃の浦添グスクは、高麗系瓦ぶきの正殿を中心に、堀や石積み城壁で囲まれた巨大なグスクで、周辺には王陵・寺院・大きな池・有力者の屋敷・集落などがあったと考えられています。
のちの王都首里の原形がここでできあがっていたようです。
 王都が首里に移された後、浦添グスクは荒廃しますが、1524 年頃から1609 年の薩摩藩の侵攻までは浦添家の居館となりました。
王都が首里に移された後、浦添グスクは荒廃しますが、1524 年頃から1609 年の薩摩藩の侵攻までは浦添家の居館となりました。去る沖縄戦では、日米両軍の激しい戦闘により、戦前まで残っていた城壁も大部分が破壊されました。
これまでの発掘調査では、石積み城壁の基礎や、敷石遺構、建物跡などが良好に残っていることが確認されています。
1989年、国指定史跡となり、史跡浦添城跡復元整備事業を進めているところです。
数十年後には世界遺産に追加登録されることが期待されます。
Posted by 特定非営利活動(NPO)法人うらおそい歴史ガイド友の会 at 14:08│Comments(0)
│浦添グスクようどれ とは
プロフィール

特定非営利活動(NPO)法人うらおそい歴史ガイド友の会
カテゴリー
最新記事
過去記事
最近のコメント
大里正史 / 「浦添城跡」扇子を販売中!
大里正史 / 研修を受けました!
大里正史 / 研修を受けました!
特定非営利活動(NPO)法人うらおそい歴史ガイド友の会 / 平和学習「前田高地の戦跡巡・・・
仲間良夫 / 平和学習「前田高地の戦跡巡・・・
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
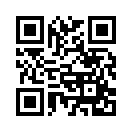
アクセスカウンタ
読者登録
















